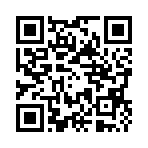正しく理解するということ
2011年06月11日
発達障害・学習障害・高機能自閉症・広汎性発達障害・アスペルガー
何がどう違うのでしょうか???
診断を見極めるためにいくつかの病院を受診したら、全て違う診断名がついた方もいるそうです。
また、成長するにつれて、高機能自閉症からアスペルガー傾向が顕著になって診断名が変わった方もいらし
ゃいます。エッジの藤堂さんは、将来これらの診断名をすべて「自閉症スペクトラム」と統一させる考え方
が主流になるとおっしゃられていました。
どの要素もそれぞれ持っていて発達段階や診断時にどの傾向が顕著に出ているかで診断名が変わってしまう
事もあるのだということです。
それぞれ連続体のものであるという考え方です。
大事なのは診断名ではなく、その子が今何に困っているか。
どの部分にサポートを必要としているか。
その子が将来幸せになるためのサポートは何かを見出すことです。
そして、正しく理解する目を持つことです。
子供たちが日常のほとんどを過ごす学校の中では特に、その理解者の存在は大きいと思います

私が長男の今までの子育ての中で感じたことは、理解無い言動や態度がいかに子供と親を傷つけるか、、、、、ということです。
ハンセン病患者の会の会長さんが「無知が差別を生む」とおっしゃっていたように
特性を持つ子供たちにとっても同じことが言えると思います。
みんなと同じことができない。
普通が難しい。
だけど、普通の子が難しい高度なことを難なくこなしてしまう高機能な特性を持った子は、教科によって学習到達度の差が大きいことを、怠け者・努力不足と思われてしまう。
状況が理解できず適切な行動が取れないことを反抗的、教師をなめていると思われてしまう。
きっと、全国の先生方、愛を持ってスキルを総動員して子供たちのために頑張っていただいていると思います。だけど、悲しいかな、特性を持っている子にはそれが通用しないんです。
ベクトルのずれが起きてきます。
先生も子供も頑張っているのに、努力の割りに成果が見合わないということが出てきます。
先生も子供も親もしんどくなってきます。
1クラス30~40人の子供に先生一人では負担が大きすぎます・・・
そんなときは、やはりサポートが必要です。それが、学習支援員(LSA)です。
子供の特性を理解し寄り添いサポートする、教師の指導の元に(教えるのはあくまで先生です)学習もサポートする。
そして、教師とLSAがうまくコミュニケーションを取り、円滑にクラスの中で機能できれば
 と思います。
と思います。実際エッジの管轄する港区では延べ230名以上のLSAが配置され、支援に付いた子供さんの不登校率はゼロ。
さらにすごいことに、高学年になるにつれ、LSAの役割や適切な対応を見て育ってきたクラスメイトが、サポート役割をするようになり、結果としてLSAは要らなくなるのだそうです。
そのような実績がでている、LSA制度。
宮崎でも当たり前の制度にしていきたいですね

こんにちは スマイルクラブです
10月3日 素敵なシンポジウムに参加しました
ひなたde子育て情報フェスタ!
今日から8月ですね、8月の茶話会は中止と致します
会員の皆様へお知らせメールの送信をしました
1月26日(日)おしゃべり会♪ おわりました^^
10月3日 素敵なシンポジウムに参加しました
ひなたde子育て情報フェスタ!
今日から8月ですね、8月の茶話会は中止と致します
会員の皆様へお知らせメールの送信をしました
1月26日(日)おしゃべり会♪ おわりました^^
Posted by Ikuyo at 00:57 | Comments(0)
| 子供 子育て 気持ち